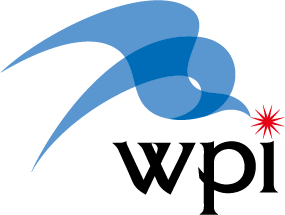酵素に注目:がんの進化を未然に防ぐ分子的アプローチ
本研究者インタビューでは、磯崎英子教授が、臨床的知見、分子生物学、そして高速顕微鏡を統合することにより取り組むがん進展予防の研究について紹介する。グローバルな経験と患者中心のアプローチに基づき、磯崎は金沢大学ナノ生命科学研究所(Kanazawa University Nano Life Science Institute: NanoLSI)で、酵素APOBEC3Aを標的としてがんの進化を未然に防ぐ研究に取り組んでいる。
薬剤師から基礎研究者へ
磯崎英子教授は、科学者としてキャリアをスタートさせたわけではない。最初は薬剤師としての教育を受けたが、安定で選択肢の広いこの職業を選んだのは、特に家庭と仕事の両立を迫られる女性にとって現実的な決断だったからである。

磯崎英子、金沢大学ナノ生命科学研究所 教授・主任研究者
「子供の頃、科学者になりたいと夢見ていました」と磯崎は振り返る。「でも、研究は才能豊かで真に独創的な人のものだと思っていました。自分には難しいと感じていました。」
歳月を経て、夫の励ましもあり、磯崎は子供の頃の夢に再び向き合った。薬剤師から科学者へと転身した彼女は、貴重な臨床的知見を携えて研究に取り組んだのである。「患者さんと関わることで、現実世界の医療ニーズを深く理解することができました」と彼女は説明する。「その視点は、今でも私が科学的な問いを考慮する際の指針となっています。」
臨床的知見と分子メカニズムの橋渡し
磯崎は薬学の基礎と幅広い疾患に関する実際の経験を活かして、総合的な考え方でがん研究に取り組んでいる。「がんは非常に複雑で、個性的です。臨床の知識と基礎研究を橋渡しすることは、とても重要です」と彼女は言う。
現在、NanoLSIに所属する磯崎は、がんの進化を促す分子機構、特に酵素APOBEC3Aの役割の解明に焦点を当てて研究を行なっている。
ボストンで鍛えられたグローバルな視点
彼女の科学的ビジョンは、マサチューセッツ総合病院・ハーバード大学医学部での約 7 年間によって深く培われた。磯崎は多文化で協力しあう環境に身を置き、小さなチームを率いて若い研究者達を指導した。「オープンな議論とチームをベースとするアメリカ流の研究アプローチは、その後の自分に大きな影響を与えました」と彼女は言う。
海外での年月を通して、彼女は日本人としてのアイデンティティをより深く意識するようになった。「同僚の多くが日本に深い関心を持っていました。彼らの日本の文化と科学に対する敬意のおかげで、私は自分のバックグラウンドを誇りに思うことができました」と彼女は言う。この経験は、今も彼女の国際的な研究協力に活かされている。
がんの進化を促す酵素を標的とする
磯崎の最近の研究は、抗ウイルス活性で知られていたが、現在ではがんにおける遺伝子変異のドライバーとして認識されている酵素、APOBEC3Aに焦点を当てている。彼女はNature誌の論文で、がん細胞のAPOBEC3A遺伝子を欠損させると、薬剤への耐性獲得が遅延することを明らかにした [1]。
「これは極めて重要な発見でした」と彼女は説明する。「耐性の獲得を待つのではなく、変異の源に介入することで耐性の予防を目指すことができるのです。」この予防的戦略は、薬剤耐性のある腫瘍が現れた後の治療に焦点を当てている従来のアプローチからの転換を示している。
彼女は以前の研究において、オシメルチニブやアレクチニブといった肺がんの治療に用いられる薬の獲得耐性メカニズムにも着目してきた [2, 3]。
酵素の作用を視覚化する
NanoLSI では、磯崎は高速原子間力顕微鏡 (HS-AFM) を活用して、APOBEC3A が DNA とどのように相互作用するかを直接観察している。このリアルタイム画像化技術は、がんが分子レベルでどのように進化するかに関するこれまでにない知見を提供する。
「酵素がリアルタイムで働いているのを観ると、突然変異に対する理解が変わります」と彼女は言う。「これにより、耐性が獲得される前に阻止できる正確なタイミングでの介入が可能になるのです。」
この物理学と生物学の統合は、NanoLSI の学際的な強みを示すものである。
金沢でグローバルコミュニティを発見
数年の海外生活を終えて日本に戻った磯崎は、狭い研究環境に戻ることを恐れていた。しかし、彼女は NanoLSI には多様性があり、前向きで、グローバルにつながっていることに気付かされた。「嬉しい驚きでした」と彼女は言う。「この国際的な雰囲気は、ボストンで働いていた頃の私がとても好きだったものです。」
NanoLSIの協力体制によって、彼女は分野を超えてパートナーシップを構築し続けることができている。「ここは、臨床での経験と最先端の顕微鏡技術との融合が実現できる場所です」と彼女は言う。
研究室外での日々のインスピレーション
多忙な研究生活を送りながらも、磯崎は個人的な時間、特に夫との何気ないひとときからインスピレーションを得ている。「美味しい食べ物や美しい景色を一緒に楽しむのが大好きです」と彼女は言う。「こんなときの会話は、課題に対処したり、新しいアイデアを思いついたりするのに役立つことが多いです。」
彼女はまた、温泉に行ったり、景色を見たりすることも楽しんでおり、そうすることによって、学問の世界の外での喜びとくつろぎがもたらされる。
若手科学者へのメッセージ
磯崎は、キャリアの浅い研究者、特に女性研究者に、心を込めてアドバイスを送る。「思い込みで目標を諦めないでください。あなたを支えてくれる人に相談してみて。あなたが前進する道を見つける手助けをしてくれるかもしれません。」
彼女はまた、自分自身の情熱について正直になるようにと、励ましている。「もし自分がしていることが嫌なら、無理をしないように。エネルギーが湧いてくることをしましょう。本当のモチベーションはそこから生まれるのです。」
磯崎教授は、酵素の顕微鏡での観察とがんの進化予防を使命として、早期の介入、国際的協力、そしてとどまるところのない科学的探究心に根ざしたがん治療の研究を推進している。
参考文献
[1] Isozaki et al., Therapy-induced APOBEC3A drives evolution of persistent cancer cells. *Nature*. 620(7973):393-401, 2023.
[2] Piotrowska*, Isozaki* et al., Landscape of acquired resistance to osimertinib in EGFR-mutant NSCLC and clinical validation of combined EGFR and RET inhibition with osimertinib and BLU-667 for acquired RET fusion. *Cancer Discov*. 8(12):1529-1539, 2018.
[3] Isozaki et al., Non-small cell lung cancer cells acquire resistance to the ALK inhibitor alectinib by activating alternative receptor tyrosine kinases. *Cancer Res*. 76(6):1506-16, 2016.
Posted: July,2025